2010年02月01日
『サッカーで子どもをぐんぐん伸ばす11の魔法』がススメ
一昨日書いた、子供の頃サッカー以外にどんなスポーツやっていたかが重要!?に続き‥
サッカーをやられている小さなお子様をお持ちの、お父さんお母さんに、『サッカーで子どもをぐんぐん伸ばす11の魔法』という本がお勧めです。
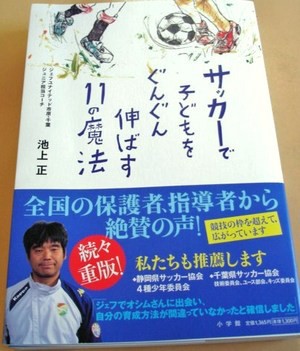
大人たちは、子どもたちへしてあげるべき本当に大切なこと見失っているのかもしれません。
↓
サッカーをやられている小さなお子様をお持ちの、お父さんお母さんに、『サッカーで子どもをぐんぐん伸ばす11の魔法』という本がお勧めです。
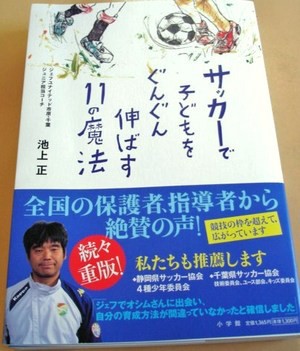
大人たちは、子どもたちへしてあげるべき本当に大切なこと見失っているのかもしれません。
↓
著者である池上正氏の肩書きは、ジェフ市原・千葉ジュニア担当コーチだそうです。
長年YMCAで指導者として勤められ、その後ジェフ千葉で少年サッカーに関わってこられたそうです。
この池上氏のこれまでの経験を元に子どもたちへのサッカー(スポーツ)の指導方法とその考え方について語られています。
ただ、この本はサッカーの指導書ではありません。
気になる11項目は‥
1 肯定する
「だからダメなんだよ!」抽象的な言葉で叱ってばかりいませんか?
*怒ったり、小言を言うより前向きに取り組める雰囲気を作ろう。
2 上達する
「悔しくないのか!」負け始めると怒っていませんか?
*勝利至上主義ではなく、フェアプレーと「いいサッカー」で、子どもはぐんぐん伸びる。
3 楽しませる
「サッカーを最優先しろ!」子どもに押しつけてはいませんか?
*サッカーは「習い事」ではなく、「遊び」です。
4 気づかせる
「ちゃんと話を聞きなさい!」いつも世話を焼いていませんか?
*転ばぬ先の杖を用意しない。できない経験をさせると、話を聞ける子に育ちます。
5 考えさせる
「右へパス!」「そこでシュートだ!」試合の間中、子どもを煽っていませんか?
*自らの力で判断できる子が「あと伸び」します。
6 進化する
「今までこうやってきたんだから」古い概念のまま立ち止まっていませんか?
*スポーツは日々進化します。頭を切り替える柔軟性と勇気を持ちましょう。
7 夢を持たせる
「プロになりたいんだよな?」子どもより先に自分の望みを語っていませんか?
*大人の期待を伝えるのではなく、子どもが自発的に目標を持てるように導こう。
8 余裕を持たせる
「勝ちたいという気持ちが足らなかった」敗戦を精神論で片付けていませんか?
*余裕を持って子どもと接すれば本質が見えてきます。
9 自立させる
「失くすと困るから」電車の切符を大人が持ってあげていませんか?
*「できること」ではなく「経験すること」を重視しよう。
10 和をつくる
能力別にチーム分けするのがよいと思い込んでいませんか?
*同じ能力、同じ年齢で構成せずに、「異の集団」で子どもは伸びる。
11 問いかける
「何やってんだ!」大量リードされたら怒鳴ってませんか?
*指示するのではなく、問いかけること。子どもから答えを引き出そう。
人それぞれの感じ方があるので、自分がここで語るより読んでもらった方が良いと思います。
あえて少し書かせて頂くと‥
池上さんは「子どもが困ったときに大人の顔を見るという状況が、日本では非常に多い」と言われています。
特に、スポーツというものは、練習したような場面がいつも実戦で出てくるわけではありません。
その都度、その都度、本当に微妙なのですが、違う状況がいっぱいでてきます。
すると、言われた通りの練習をやってきただけの子どもたちは、そういう状況に対応できません。
そこで、自分たちが思うように出来ない時、子どもたちが試合でどうするかと言うと、間違いなくコーチの顔を見ます。
「コーチ、どうしたらいいの?」と。
サッカーの試合中、子供がしょっちゅうベンチを見ているチームが目につきます。
そのチームからは決して良いプレーヤーは生まれないと思うのです。
中には、子どもに指示は出すけれども、言うとおりにするか、しないかは子どもの判断に任せている方もあります。
そういうコーチは自分の経験でわかっているのです。
自分たちの言う事を聞く子より、いう事を聞かない子の方が、後で伸びているということを‥
なので、指導者には試合でも練習でも、子どもが自分で考えると言う場面を常に引き出すように心がけてもらいたい。
練習でもいつも子どもを煽っているだけで、子どもに考えさせる機会や時間を与えていないコーチが多すぎます。
「言われた通りに出来る子」ではなく、「自分で考えられる子」に育てて欲しいのです。」
また子育てにおいて、大人は子供が何か失敗をすると頭ごなしに叱ってしまいがちです。
子供の意見をあまり聞かずに、大人の意見を無理やり子供達に押しつけていませんか?
そういう自分も‥ 読んでいて恥ずかしくなりました。
子供達には本来気づく力、考える能力があります。
一方的に親の期待などを押し付け過ぎると子どもはその重圧に押しつぶされてします。
敗戦したときの指導者の発言に。
「勝ちたいと思う気持ちが足りなかった」
「相手のほうが、勝ちたいと思う気持ちが強かった」
などと精神論で総括したり。
「今日はミスばっかりしてたね」
「どうしてそんなにミスしたの」
「あんなにミスすると勝てないよ」
これらの敗戦理由は、「間違いなく負けたことを子どものせいにしている‥」との事。
指導者として具体的な改善方法が思い描けないにもかかわらずミスばかりを指摘しても何も進化は生まれない。
そういえば、某チームのY監督もよく同じようなコメントしてたなぁ‥
これは全部選手(子供達)が悪いって罪をなすり付けていたのかもしれません。
ここ数年ジュビロの選手達もよく監督の指示を仰ぐためか?ベンチをキョロキョロしてます。
数年前なら自分達だけで状況を打開出来る選手がいたからでしょう。
今では監督の指示がないと動けないのです。
きっと失点して不安で仕方が無いのでしょう。
プロでさえこの程度なのですから‥
あと気になったのは‥
ブラジル、ヨーロッパのどこの国でも、小学生年代の全国大会は開催されていないのだそうです。
開催されているのは、日本、韓国など、東アジアの国だけで、かつてブラジルでも開催していた時期もあるらしいけれど、やめてしまったという。
理由は、選手が育たなかったためだそうです。
小学生年齢で11人制サッカーをしているのは、日本、中国、韓国の東アジアの国だけで、サッカー先進国では、小学生の全国大会をやらないだけではなく、そもそも11人制のサッカーをしていないらしいです。
オランダでは4対4、イギリスでは7対7や8対8が中心だそうです。
サッカーの基本中の基本は、トライアングル、つまり2方向へパスをだせる状況をつくることなので、少人数制のサッカーで、基本を身体に覚えこませるというのが、サッカー先進国の選手育成のありかたのようです。
こんなコーチが下部組織にいらっしゃるなんて、ジェフの未来は明るいと思います
サッカーのみならず、子育てに対する良いバイブル、一度読んでみる価値あります。
書店に無い場合は、アマゾン↓なら即届きますよ。

☆関連記事
中村俊輔 夢をかなえるサッカーノート 買ってみました!
http://ke1224.hamazo.tv/e1852691.html
脳を生かす子育て
http://ke1224.hamazo.tv/e1549397.html
宜しければランキング応援もお願いしますm(__)m

長年YMCAで指導者として勤められ、その後ジェフ千葉で少年サッカーに関わってこられたそうです。
この池上氏のこれまでの経験を元に子どもたちへのサッカー(スポーツ)の指導方法とその考え方について語られています。
ただ、この本はサッカーの指導書ではありません。
気になる11項目は‥

1 肯定する
「だからダメなんだよ!」抽象的な言葉で叱ってばかりいませんか?
*怒ったり、小言を言うより前向きに取り組める雰囲気を作ろう。
2 上達する
「悔しくないのか!」負け始めると怒っていませんか?
*勝利至上主義ではなく、フェアプレーと「いいサッカー」で、子どもはぐんぐん伸びる。
3 楽しませる
「サッカーを最優先しろ!」子どもに押しつけてはいませんか?
*サッカーは「習い事」ではなく、「遊び」です。
4 気づかせる
「ちゃんと話を聞きなさい!」いつも世話を焼いていませんか?
*転ばぬ先の杖を用意しない。できない経験をさせると、話を聞ける子に育ちます。
5 考えさせる
「右へパス!」「そこでシュートだ!」試合の間中、子どもを煽っていませんか?
*自らの力で判断できる子が「あと伸び」します。
6 進化する
「今までこうやってきたんだから」古い概念のまま立ち止まっていませんか?
*スポーツは日々進化します。頭を切り替える柔軟性と勇気を持ちましょう。
7 夢を持たせる
「プロになりたいんだよな?」子どもより先に自分の望みを語っていませんか?
*大人の期待を伝えるのではなく、子どもが自発的に目標を持てるように導こう。
8 余裕を持たせる
「勝ちたいという気持ちが足らなかった」敗戦を精神論で片付けていませんか?
*余裕を持って子どもと接すれば本質が見えてきます。
9 自立させる
「失くすと困るから」電車の切符を大人が持ってあげていませんか?
*「できること」ではなく「経験すること」を重視しよう。
10 和をつくる
能力別にチーム分けするのがよいと思い込んでいませんか?
*同じ能力、同じ年齢で構成せずに、「異の集団」で子どもは伸びる。
11 問いかける
「何やってんだ!」大量リードされたら怒鳴ってませんか?
*指示するのではなく、問いかけること。子どもから答えを引き出そう。
人それぞれの感じ方があるので、自分がここで語るより読んでもらった方が良いと思います。
あえて少し書かせて頂くと‥
池上さんは「子どもが困ったときに大人の顔を見るという状況が、日本では非常に多い」と言われています。
特に、スポーツというものは、練習したような場面がいつも実戦で出てくるわけではありません。
その都度、その都度、本当に微妙なのですが、違う状況がいっぱいでてきます。
すると、言われた通りの練習をやってきただけの子どもたちは、そういう状況に対応できません。
そこで、自分たちが思うように出来ない時、子どもたちが試合でどうするかと言うと、間違いなくコーチの顔を見ます。
「コーチ、どうしたらいいの?」と。
サッカーの試合中、子供がしょっちゅうベンチを見ているチームが目につきます。
そのチームからは決して良いプレーヤーは生まれないと思うのです。
中には、子どもに指示は出すけれども、言うとおりにするか、しないかは子どもの判断に任せている方もあります。
そういうコーチは自分の経験でわかっているのです。
自分たちの言う事を聞く子より、いう事を聞かない子の方が、後で伸びているということを‥
なので、指導者には試合でも練習でも、子どもが自分で考えると言う場面を常に引き出すように心がけてもらいたい。
練習でもいつも子どもを煽っているだけで、子どもに考えさせる機会や時間を与えていないコーチが多すぎます。
「言われた通りに出来る子」ではなく、「自分で考えられる子」に育てて欲しいのです。」
また子育てにおいて、大人は子供が何か失敗をすると頭ごなしに叱ってしまいがちです。
子供の意見をあまり聞かずに、大人の意見を無理やり子供達に押しつけていませんか?
そういう自分も‥ 読んでいて恥ずかしくなりました。
子供達には本来気づく力、考える能力があります。
一方的に親の期待などを押し付け過ぎると子どもはその重圧に押しつぶされてします。
敗戦したときの指導者の発言に。
「勝ちたいと思う気持ちが足りなかった」
「相手のほうが、勝ちたいと思う気持ちが強かった」
などと精神論で総括したり。
「今日はミスばっかりしてたね」
「どうしてそんなにミスしたの」
「あんなにミスすると勝てないよ」
これらの敗戦理由は、「間違いなく負けたことを子どものせいにしている‥」との事。
指導者として具体的な改善方法が思い描けないにもかかわらずミスばかりを指摘しても何も進化は生まれない。
そういえば、某チームのY監督もよく同じようなコメントしてたなぁ‥
これは全部選手(子供達)が悪いって罪をなすり付けていたのかもしれません。
ここ数年ジュビロの選手達もよく監督の指示を仰ぐためか?ベンチをキョロキョロしてます。
数年前なら自分達だけで状況を打開出来る選手がいたからでしょう。
今では監督の指示がないと動けないのです。
きっと失点して不安で仕方が無いのでしょう。
プロでさえこの程度なのですから‥
あと気になったのは‥
ブラジル、ヨーロッパのどこの国でも、小学生年代の全国大会は開催されていないのだそうです。
開催されているのは、日本、韓国など、東アジアの国だけで、かつてブラジルでも開催していた時期もあるらしいけれど、やめてしまったという。
理由は、選手が育たなかったためだそうです。
小学生年齢で11人制サッカーをしているのは、日本、中国、韓国の東アジアの国だけで、サッカー先進国では、小学生の全国大会をやらないだけではなく、そもそも11人制のサッカーをしていないらしいです。
オランダでは4対4、イギリスでは7対7や8対8が中心だそうです。
サッカーの基本中の基本は、トライアングル、つまり2方向へパスをだせる状況をつくることなので、少人数制のサッカーで、基本を身体に覚えこませるというのが、サッカー先進国の選手育成のありかたのようです。
こんなコーチが下部組織にいらっしゃるなんて、ジェフの未来は明るいと思います

サッカーのみならず、子育てに対する良いバイブル、一度読んでみる価値あります。
書店に無い場合は、アマゾン↓なら即届きますよ。

☆関連記事
中村俊輔 夢をかなえるサッカーノート 買ってみました!
http://ke1224.hamazo.tv/e1852691.html
脳を生かす子育て
http://ke1224.hamazo.tv/e1549397.html
宜しければランキング応援もお願いしますm(__)m
Posted by nyantomo1546 at 20:05│Comments(7)
│★ジュビロ磐田
この記事へのコメント
この本、サッカー協会少年委員会のおススメでもあります。
また、昨年著者を招いて指導者セミナーを開きました。
協会の方も大会のあり方や指導法、親との関係などについていろいろ対策を考えています。
そのひとつとして、少年サッカーも今年から5年生までは8人制に完全移行なります。
また、昨年著者を招いて指導者セミナーを開きました。
協会の方も大会のあり方や指導法、親との関係などについていろいろ対策を考えています。
そのひとつとして、少年サッカーも今年から5年生までは8人制に完全移行なります。
Posted by JUNパパ at 2010年02月01日 07:02
at 2010年02月01日 07:02
 at 2010年02月01日 07:02
at 2010年02月01日 07:02JUNパパさん
そうですね!書き忘れましたが、静岡県サッカー協会のお勧めになっていました。
>そのひとつとして、少年サッカーも今年から5年生までは8人制に完全移行なります。
5年生以下は8人制に移行されるんですね。
県サッカー協会の対応にも期待です!
子供達の育成に良い効果が出るとイイですね。
そうですね!書き忘れましたが、静岡県サッカー協会のお勧めになっていました。
>そのひとつとして、少年サッカーも今年から5年生までは8人制に完全移行なります。
5年生以下は8人制に移行されるんですね。
県サッカー協会の対応にも期待です!
子供達の育成に良い効果が出るとイイですね。
Posted by なんでもオヤジ at 2010年02月01日 12:23
at 2010年02月01日 12:23
 at 2010年02月01日 12:23
at 2010年02月01日 12:23こんにちは。
読みましたよぉ!!
子(特にサッカーや、スポーツをしている)を持つ
親には、必読ですよね。
読み終えて、ただただ反省している自分がいました。
親を成長させてくれる一冊です。
読みましたよぉ!!
子(特にサッカーや、スポーツをしている)を持つ
親には、必読ですよね。
読み終えて、ただただ反省している自分がいました。
親を成長させてくれる一冊です。
Posted by 鉄匠館 at 2010年02月01日 12:51
at 2010年02月01日 12:51
 at 2010年02月01日 12:51
at 2010年02月01日 12:51鉄匠館さん おはようございます。
鉄匠館さんはもう読まれたんですね(^^
さすがです!
自分も読んで反省ばかり、もう一度一から子育てしたくなりました(^^;
鉄匠館さんはもう読まれたんですね(^^
さすがです!
自分も読んで反省ばかり、もう一度一から子育てしたくなりました(^^;
Posted by なんでもオヤジ at 2010年02月02日 09:35
at 2010年02月02日 09:35
 at 2010年02月02日 09:35
at 2010年02月02日 09:35あら嬉しいですね~!私も読んでみます!千葉だから多分、でかでかとおいてあると思います!
ちなみに池上正さんは、サッカーおとどけ隊っていう地域にサッカーを教えにいくっていうチームの隊長なんです(^_-)
サッカー普及チームって感じですかね?
でも、その数は凄いんですよ(^_-)
ちなみに池上正さんは、サッカーおとどけ隊っていう地域にサッカーを教えにいくっていうチームの隊長なんです(^_-)
サッカー普及チームって感じですかね?
でも、その数は凄いんですよ(^_-)
Posted by ともちゃん at 2010年02月07日 07:33
ともちゃん
まだ池上さんはいらっしゃるんですね!
もし退団されたら、是非磐田に来て頂きたいと思って(^^;
サッカーおとどけ隊ですか!いい活動されてますね。羨ましいです。
まだ池上さんはいらっしゃるんですね!
もし退団されたら、是非磐田に来て頂きたいと思って(^^;
サッカーおとどけ隊ですか!いい活動されてますね。羨ましいです。
Posted by なんでもオヤジ at 2010年02月07日 11:16
at 2010年02月07日 11:16
 at 2010年02月07日 11:16
at 2010年02月07日 11:16池上さんの著書『サッカーで子どもをぐんぐん伸ばす11の魔法』を読んで以来、池上さんのファンです。その池上正さんの3冊目が2011年9月14日に発売しています。
『サッカーで子どもの力をひきだすオトナのおきて10』です。
私は予約して購入したのですが、
より納得のいく具体的な話が書かれていて、DVDで映像確認しながら読み進めることができます!
11の魔法や、7つの目標を読まれた方には、やはりオススメです。失礼しました。
『サッカーで子どもの力をひきだすオトナのおきて10』です。
私は予約して購入したのですが、
より納得のいく具体的な話が書かれていて、DVDで映像確認しながら読み進めることができます!
11の魔法や、7つの目標を読まれた方には、やはりオススメです。失礼しました。
Posted by 初めまして at 2011年09月25日 15:43
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。











